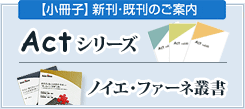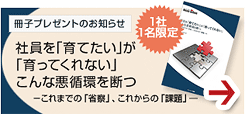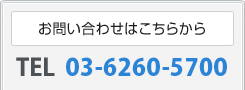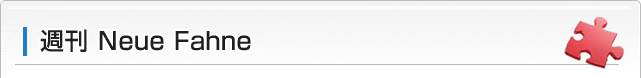人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年01月06日号
OJTによる育成手法の再考-4-情報処理と伝達に最大限の注意を払う
部下が上司に対して“この上司は頼りにならない”と認識するのは、必要とする情報を必要な人にもたらしていない場合である。上司にとって仕事を展開するうえでの必要な情報を部下に共有できていない状況がもっとも危険である。
情報伝達や情報共有とは、単に生データを上から下に垂れ流すことではない。このような情報伝達のやり方に終始してしまう上司は、ただ上から伝え聞いたそのままの状態の情報を部下に仲介している伝書鳩に過ぎないことになる。上司に求められるのは取得した情報を解析した後に導き出される知見や、特定の意思決定のために役立つ情報を伝達することである。
上司が情報を扱う場合に必要となるのは、自らが情報のコントロールタワーとして必要な情報を必要な人に相応に取捨選択、ないし加工して伝達するというハンドリングである。残念なことに多くの職場ではハンドリング以前の問題が多く発生してしまう。
この理由の多くは上司と部下との間の会話不足である。ただし、ここでいう会話とは「お喋り」を意味するものではない。端的にいえば文書やメールによる指示などであっても明確な意思の疎通が取れているのであれば「会話」は成立していることになる。
一般的にいえば上司は、その立場にあることにより会社の経営戦略に関する情報、新しい技術の情報、競合の情報、重要顧客の動向、政府関係の規制に関する情報など、ありとあらゆる情報が会社から社内メールやその他の手段で提供されるはずである。仮に部下を持つ身であるにもかかわらず、この種の情報を保持していないと自覚するのであれば、先ずは自らの不明を恥じるべきである。
会社から提供される経営に資する各種の情報は、全ての従業員に等しく提供されるものではない。あくまでも職位や職域によって提供される情報のレベルが異なるものである。いうならば社内データに対してのアクセス権が職位によって異なるようなものである。このため保有している情報の質がその者の組織におけるステータスにも直結する。
部下は上司のこの社内におけるスタータスを実に敏感に察知するものである。上司が保持している情報レベルの範囲で、上司の社内における立場を判断するといっても過言ではない。部下が上司の保有する情報レベルが自分と大差ない場合には当然にも「この上司は果たして今後とも頼りになるのだろうか…」と疑問を持つことになる。一方で仮に自分と同レベルの情報しか保持していなくとも、断片的で漠然とした情報からその意味することを推定することができる上司は一目置かれることになる。
部下から「頼られる上司」は、さまざまな情報の中から自分の部署の特定のメンバーに関係しそうな情報を取り出し、適切な指示とともにその情報に対し信憑性を吟味した上で解釈を施したものとして提供すことができる。一方、「頼られない上司」は、自分が取得した情報を無差別に部下全員に転送するなどの愚行を行うものである。最悪の場合には情報の持つ意味が理解できず何もせず放置する。この種の上司は情報が適切なタイミングで適切な人に伝わることが価値を生み出すことを知らないのである。情報が価値を生むメカニズムを知らない上司は、間違いなく「頼りにならない上司」と誹りをうけることになる。
| 一覧へ |
![]()