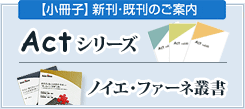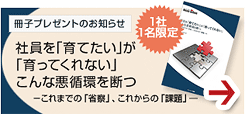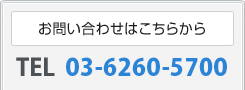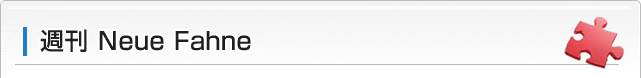人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2018年01月09日号
現場マネジメントの課題 -15- 組織改革に必要な人材の最適配置
企業は組織体制の不備によりさまざまな軋轢が発生する。一方でこの軋轢は組織にある種の刺激や活性化を生み出しプラスに作用する場合もある。逆に組織体が硬直してしまうならば、組織それ自体が自己増殖し始める場合もある。企業組織における組織の自己増殖とは、組織体を構成している人びとが個々に属する部門での「部門利益」が、「全体利益」を凌駕して一人歩きしはじめるということだ。
この傾向は黎明期の企業組織ではあまり気にならない。何故ならば、所詮「部門利益」といっても、全体から見渡せる規模であるからだ。しかし、組織の成長とともに部門構成も拡大し、権限や役割の機能化に伴い全体から見えなくなりはじめる。この結果、「部門利益」を優先する意識が頭をもたげてくるものだ。
たとえば新プロジェクト形成に向けて各部門から人材を集める場合などでは、部門の責任者は往々にして自部門の第一線級を出し渋る。そして、どちらかというと部門のなかで“もてあまし人材”を送り込むケースがある。これなどは「部門利益」を優先する典型であり、何時しか全体の最適性よりも部門最適を追求しはじめ、結果的に「部門利益」集団が形成されるようになる。
本来、企業組織は機能体として存在するものであり、組織の掲げる目的を実現させるために人材やその他の資源を集め、役割分担や指揮命令系統の整備を行っていくものだ。ところが、「部門利益」集団が形成されことで、あたかもそれぞれの部門を構成する一人ひとりのために組織が存在するかの様相を呈しはじめる。知らず知らずに個々の部門を構成する者の満足感を高めることが重要なテーマとなった「共同体」組織のように動きはじめる危険性があるということだ。
大組織などが幾度も組織改革を試みてもいつしか頓挫することがある。これは組織のだれしもが総論としては「改革」の必要性を理解しているが、各論になると自部門の利益を優先させるという構図の典型である。しかし、これは単に大組織に限ったことではない。
何故ならばそれぞれの部門を構成する人的要素も大きな桎梏になるからだ。
特に部門の立ち上げ時からの構成メンバーの人間的繋がりは、全体の利益を凌駕するほど大きなパワーを発揮する傾向がある。いわゆる「同じ釜の飯を食った」という極めてウェットな関係である。この傾向は中小企業にあらわれがたちだ。もちろん健全な人間関係を全否定する必要はない。しかし、人的関係が強固であればある程、組織の統制は効きにくくなるのも現実的なところだ。
組織改革の大前提は、“組織はあくまでもその存在そのものに価値があるのではなく、組織による成果に価値があり、その「成果」を通じて社会に貢献するものである”という位置づけだ。組織とはそれ自体が「目的」ではなく、あくまでも目的の「達成手段」である。この前提を堅持しなければ、組織を構成する一人ひとりがいくら「合理的に判断」していると感じていても、それは部分適性に過ぎず全体として「不合理」を形成してしまうということになる。全体として「不合理」に見える組織体とは、組織内部では「不条理」がまかり通っていることになり、結果として内部統制が効かなくなる。
そこで、必要になるのが部門利益の意識を解消させ、全体利益に還元させていくための人材の適正配置ということだ。つまり、適切な配置転換も必要ということだ。業務に精通した者を他の部門に異動させるのは非常に非効率に思われるが、部門利益集団化を防ぐことにもなる。ともすると組織改革は、スターの登場によってもたらされる“成功物語”化されがちだが、現場マネジメントにとってクールに組織実態を眺めた適正でシビアな人材の最適配置が必要である。
| 一覧へ |
![]()