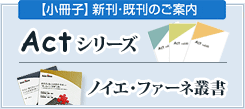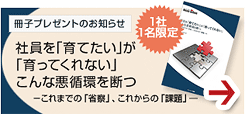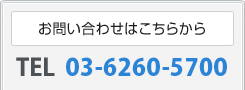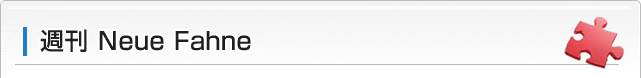人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2011年01月03日号
主役は自分自身である
会社という組織の中でその構成員である自分が「リーダーシップ」を自覚した働きに徹することと、周りとの「チームプレー」を重視した働きを展開していくことは一対の関係にある。これは経営者にとっても同じことだ。経営者としてリーダーシップを発揮していると思っていても、従業員(つまり周りの人びと)を上手く導くことができなければ、組織は組織体をなさない。単なるワンマンプレーヤーの域を出ないものだ。
経営陣が率先して一人ひとりの従業員に周りを巻き込んでいくリーダーシップを求める姿勢を示し、自らも実践で示していく必要がある。
社員研修などではよく「チームビルディング」という手法が用いられる。これは、組織全体として「ある目的」を達成するために、組織を構成するチーム員での共通認識と相互理解を深めて、有機的にチーム全体としての能力の向上を図るというものだ。研修のスタート時点では、それぞれがバラバラに動き、統制した働きを造ることができない。しかし、次第に研修参加者が自らの役割を自覚しながら他の参加者の得手不得手を理解しながら全体としての成果を出すようにそれぞれが工夫していくというものだ。そして、いつしか全体の中の一個人であっても、それぞれリーダーシップを発揮して全体として掲げた目標を達成していくことの重要性に気付かせる。
企業がこうした研修を取り入れる背景には、一人ひとりの社員の力の集合値に相乗効果が生まれていないという問題があるからだ。つまり、1人+1人の力が単純に2人の足し算にとどまり、それ以上の効果を発揮できていないということだ。
企業という組織での活動では、自分自身の能力はいうまでもなく、チームとしての相乗効果を生み出していく活動が不可欠となってくる。従って、一人ひとりの社員に「リーダーシップ」の感覚が求められ、一人のスーパーマンの存在はむしろ組織の阻害にさえなってくることさえあるものだ。
一人ひとりに求められるのは、会社という組織全体の成功を自分自身の成功と捉えることができる意識性である。同時に自分以外の周りの人びととも相互に影響力を行使し合いながらが、相乗性のある働き方をしていくことだ。
もちろん会社組織には、経営者に始まり各階層において管理者等のリーダーが存在している。だが、会社組織の主役は自分自身であり、一人ひとりの社員であることを自覚する必要がある。自分が会社組織の「推進役は自分だ」と思うくらいの感覚が必要だ。「いわれた通りにやっていればいい…」「最終的には上司の意見が通るのだから、異議をはさまないほうが…」こうした姿勢を取っていては、自分自身の日常の業務実践を卑下するのと同じである。
自分自身がリーダーと同じ意識で行動して、推進役となることで、自分自身に「リーダーシップ」が形成されてくるものだ。
| 一覧へ |
![]()