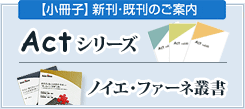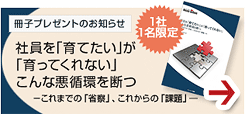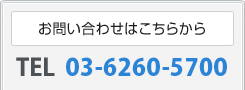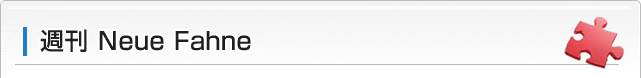人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年07月07日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-6-部下を“認める”力と勇気
職場において、若手社員との接し方に悩む管理職は少なくない。上司という立場の役割は、単に業務を指示することではない。部下を支え、導き、成長を促す存在であるべきであり、そのためには、いくつかの前提となる姿勢が求められる。
部下に対して責任を持つのは、あくまでも直属の上司である。面倒を見るのも、指示を出すのも、進捗を確認するのも、最前線に立つのは直属上司の役割だ。上司はルールや期限を明確に示し、部下の状態を把握したうえで行動すべきであり、決して業務を丸投げしてはならない。また、上司を含む年長者は、若手に対して「わかったふり」をすべきではない。分からないことは素直に認め、共に考える姿勢こそが、信頼の土台となる。
こうした前提のもとで、若手との関わりには「教える」「訓練する」という姿勢が求められる。指導という言葉は、ともすれば一方的な上意下達の印象を与えがちだが、実際には丁寧に説明し、実践を通じて習得させることの方が重要である。若手が躊躇している場面では、その場に手を差し伸べることをためらってはならない。経験が浅い彼らにとって、最も安心できるのは、「見てくれている」「支えてくれている」という実感なのである。
一昔前と異なり、年長者の“武勇伝”は若者には響かない。むしろ害になることすらある。語るべきは過去の成功ではなく、むしろ失敗と、その挽回の過程である。情意のある経験談こそが、彼らの共感を呼び、学びのきっかけとなる。また、若者は「現役」(実際に挑戦している人)を尊敬する傾向が強い。たとえ50代・60代であっても、自ら挑戦し、リスクを取る姿を見せなければ、信頼は得られない。失敗してもなお起き上がり、再び挑む背中を見せることこそリーダーの姿である。
部下との信頼関係を築くうえで、特に重要なのは「早い反応」である。報告書や日報、提案書など、部下が提出した書類を放置してしまえば、彼らのやる気は一気に冷めてしまう。高い評価よりも、まずは“早く評価する”という姿勢が求められる。部下は自分の行動がどう受け止められたかに敏感であり、「上司は読んでくれているのか」「自分の企画は的外れだったのか」と不安を抱くものだ。その不安に迅速に応えることこそが、信頼を深める第一歩である。
この原則は、日常の報告や会話においても同様である。成果への評価はもちろん、途中の苦労や、仕事を終えた後の気づき・提案に対しても、上司の反応があるかどうかが極めて重要となる。特に、不手際への指摘には細心の注意が必要だ。ただ叱るのではなく、「どうしてそうなったのか」「次はどうすればよいか」を共に考えることで、部下は前向きに受け止め、成長していく。
こうした関わりの積み重ねが、「人望」を築くことにつながる。人望とは、相手の価値を認め、正しく評価できる力である。どれほど知識や経験があっても、人望がなければ、部下はついてこない。上司が肩書きや年齢、過去の栄光をふりかざすような姿勢では、部下の信頼を得ることはできない。中途半端な権威を背景に強制するのではなく、「この人の言葉なら聞く価値がある」と思わせる経験と姿勢を持ち合わせているかどうかが問われる。さもなければ、その振る舞いは滑稽なものになる。そもそも、上下関係における実力や知識の差など、たかが知れている。むしろ、部下の方が優れている点も多い。その現実を謙虚に受け止め、自らの権威に固執せず、相手を認める力を持つこと。それこそが人望の源であり、リーダーとしての最大の資質である。
部下が「自分は正しく評価されている」と感じたとき、彼らは自らの意思で動き出す。その内発的な動機こそが、組織を活性化させる最大のエネルギーとなる。管理職とは、組織を束ねる存在である以前に、一人ひとりの存在を認め、信頼し合える関係性を築く存在である。部下の力を引き出すのは、命令や叱責ではない。彼らの存在を認め、価値ある存在として接する“勇気”と“覚悟”こそが、真のマネジメントである。その力を磨き続けることが、管理職としての成長であり、自身の成熟でもある。
| 一覧へ |
![]()