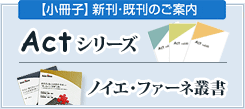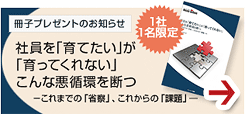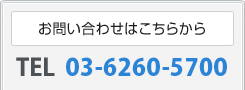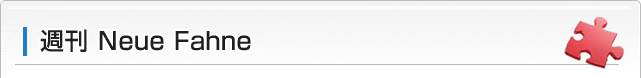人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年06月30日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-5-部下・若手社員からも真摯に“学ぶ”
「上司は部下を理解するのに三年かかるが、部下は上司を三日で見抜く」といわれる。確かに、部下は上司の言動や立ち居振る舞いをよく観察している。上司とは、単なる職位ではなく、会社から部下を預かり、その成長に責任を持つ存在である。その責任を果たすために必要なのは、何よりも真摯に部下と向き合う姿勢である。「部下に真摯に接する」ことは、部下指導の原点であり、指導する側の心構えでもある。自らの態度を省みて、悪しき言動を戒め、部下の変化に対応するだけの“許容量”を広げていくことが求められている。
とりわけ現代の若手社員は、従来型の指導では動かない。彼らはリスク回避傾向が強く、「失敗から学ぶ」ことを当然とは考えない。大人世代が語る「若いころの苦労話」や「試行錯誤の大切さ」といった経験則が響かないばかりか、時に有害にも作用する。そもそも若者たちは、幼少期からの教育環境において失敗経験そのものが乏しい。試行錯誤を通じて成長する、という前提自体が通用しない。だからこそ、上司や先輩が一方的に語るのではなく、自分の過去の“失敗談”と、それをどう乗り越えたかを丁寧に伝えることが重要となる。
現場マネジメントにおいても、若手社員の言動や価値観の変化を単なる「理解」で終わらせてはならない。大切なのは、その変化に“適応する”ことである。今日の若手社員は、バブル崩壊やリーマンショックといった社会的混乱を子ども時代に体感し、多様な価値観と向き合いながら成長してきた。安定を求める者もいれば、自分らしさを大切にしながら働きたいと願う者もいる。こうした多様な志向性に応じて、現場での指導法や働きかけ方も柔軟に変えていかなければならない。
また、若手は指示されたことをただ受け入れるのではなく、「なぜそれをやるのか」という理由を求める傾向が強い。昭和的な精神論や命令口調は、もはや効果的ではない。むしろ、業務の背景や目的を明確にし、分かりやすく丁寧に伝えることが基本となる。言葉の使い方ひとつ、指示の出し方ひとつで、相手の受け止め方は大きく異なる。マネジメントに求められるのは、かつてのような「一を聞いて十を知れ」という期待ではなく、「十を説明して一を実行してもらう」くらいの達観した姿勢である。
忘れてはならないのは、若手社員との関係においても“学びは双方向である”という原則である。上司は教えるだけでなく、若手から学ぶ意識を持たなければならない。教育制度の多様化を背景に、若手社員は他者の立場や感情に対して敏感であり、多様性を受け入れる柔軟性も持っている。彼らの言動の奥にある価値観や行動様式を、単なる「甘え」や「未熟さ」と切り捨てるのではなく、自らの学びの対象として受け止める姿勢が必要だ。
そのためには、上司自身が挑戦を続ける姿を見せることが不可欠である。若者は「現役選手」にしか敬意を払わない。年齢や立場に関係なく、自らリスクを取り、失敗し、それでも立ち上がる姿を見せることでこそ、若手社員との信頼関係が築かれる。「次こそ成功させたい。力を貸してくれ」と頭を下げて協力を求めることは、指導者としての弱さではなく、むしろ人としての強さである。
直属の上司は、部下に対する責任を担う立場である以上、業務の丸投げを避け、ルールや期限を明確にしたうえで手を差し伸べる姿勢が求められる。教えるという行為は、単なる説明や命令ではなく、相手の理解度や背景を踏まえながら“訓練”として粘り強く関わる行為である。
結局のところ、職場における成長とは、一方的な教示では成り立たない。教える側も学び続ける存在でなければならない。若手社員の変化に戸惑うだけでなく、そこに何を見出し、自分自身のマネジメントにどう活かしていくか。その問いに真摯に向き合うとき、上司と部下の関係性は、単なる上下にとどまらず、共通の目的の下での協働に向け互いに磨き合う“学び”の機能体として駆動し始める。
| 一覧へ |
![]()