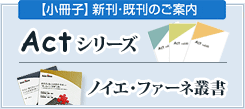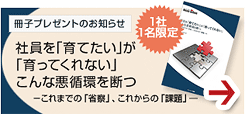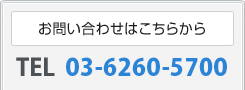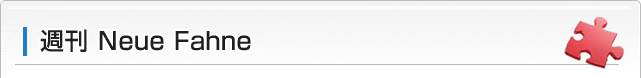人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年06月23日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-4-改めてマネジメントと管理職の役割を問う
自らが所管する職場を構成する一人ひとりの“働きの姿勢”は、現場マネジメントの姿勢を映し出す鏡である。つまり、現場の状態は現場責任者の能力のみならず、会社全体の組織力をストレートに反映する。個々の働き手がどれだけ効果的に仕事を展開しているのかは、所管する職場において構成員をどのようにマネジメントするかによって決まる。
現場マネジメントは常に“市場や購買者という買い手の立場に立って、買い手が必要とするものを提供していく”という「マーケット・イン」発想を堅持するということである。この発想の欠如、すなわち一方的な「プロダクト・アウト」思考がクレーム発生の温床になることを忘れてはならない。従って、現場マネジメントは常に所管するエリアの市場動向に対しても敏感にアンテナを張りめぐらしていかなければならない。
現場マネジメントの担い手(一般的には管理職)は、単に自分一人が売上や利益を追求することではない。自ら与えられた職責(役割)を果たし、自らの存在で所管する部門・部署に影響を与えて全体的な業績向上に寄与することである。職場に影響を与えるということは、すなわち一人ひとりが職種と職位・職階にかかわらず、自らの役職においてそれぞれの“リーダーシップ”を発揮するということである。
現場マネジメントの担い手は、所管する部署の業績に直結する事柄の全体に責任を持たなければならないということである。これは自らが所管する部門・部署の〝経営者〟であるという意味であり、所管する部門・部署の単なる利益代表者であってはならないということである。また、自らに課せられている数値のみを追求するのではなく、組織体としての成果を作り出していかなければならない。自分が頑張れば良いということではなく、雇用形態の違いにかかわらず勤怠も含めた所管する部門・部署の全構成員への業務指導及び職場環境の維持と改善にも責任を負うということである。
現場における人事マネジメントは管理部等の特定された部門・部署、担当の専任業務ではなく、現場マネジメントの担い手の基本的な職務範疇である。なぜならば所管する部門・部署を構成している「生身の人間」は、遠隔操作ではなく現場の場長の指導の下にあるからである。つまり、現場マネジメントの担い手は、現場を構成する人的資本の成長に対しても責任を持たなければならないという意味でもある。
人的資本の成長に寄与する現場マネジメントの担い手は、自ずと自らの成長を促すことになる。逆に現場の人的資本を構成する一人ひとりを成長させることができない現場マネジメントの担い手は、自らも成長することはできない。自らの成長を担保できるのは自律(セルフコントロール)と自立的な“学び”に他ならない。
管理職は部下に対して必要以上に「働きかけ」をする必要はない。「やる気がない」と見える部下に対して「如何にしてやる気を出させるか」という問題設定は、あくまで、問題の所在を「部下」においている視点である。つまり、「相手が変わるべきである」という思考である。この思考の先には、目標達成に向けた手段として「人を変える」という不確実なことを追求することになる。相手を変えるという「不確実性」にエネルギーを用いる必要はない。管理職の役割は「部下を変えること」や「部下にやる気を出させること」でもなく、「部下を通じて成果を出すこと」である。
追及すべきは部下が変わらなくても組織として「成果」が出る仕組みを構築することである。「部下」の内面的な事柄を問題にするのではなく、部下が「成果を出す仕組み」に焦点を当てることである。マネジメントは「人」を管理することではない。従って、一人ひとりの部下に「やる気」があるか否かを問題にすべきではない。どんなに「やる気」にあふれたメンバーが揃っていたところで組織として「成果」が出ていなければ意味がない。
| 一覧へ |
![]()