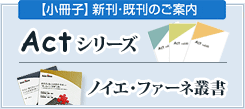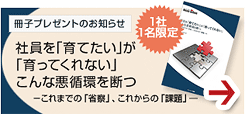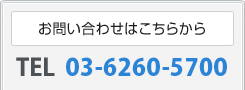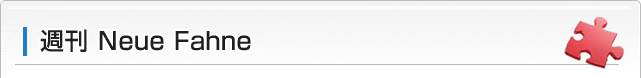人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年06月16日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-3-管理職は「罰ゲーム」なのか?
「管理職の罰ゲーム化」といわれ始めて久しいが、今では「管理職の罰ゲーム化」という揶揄とも自嘲つかない表現が根づいている。「管理職の罰ゲーム化」といわれる所以は、日本の管理職に対して「責任が増す一方で、それに見合ったメリットが感じにくい環境が広がっている」という現象であるらしい。今日の管理職を取巻く環境としての「時間外労働の増加」「職場の人間関係」「過剰な責任とストレス」に見合った「評価や報酬」が伴っていないというものである。
さらには、業務の成果や部下のパフォーマンスに対する責任が増すことになるため、過剰なプレッシャーやストレスを抱えることが多くなる。このため、かつては昇進やキャリアアップの象徴とされていた管理職が、逆にストレスの多い「損な役回りになっている」と見なされ始めているというものだ。入社した企業で勤め上げることが美徳であるかのように錯覚していた時代には、一定の経年に伴い管理職に昇格することが既定路線であるかのように捉えられていた。しかし、この既定路線が実は「損である」と思えるようになり、「ババを引く」として捉えるようになったというものだ。
「罰ゲーム化」という言説が拡大したのには相応の訳がある。それはバブル崩壊以降、日本の多くの企業において従来のピラミッド型だった組織の形式的なフラット化の傾向が始まったからに他ならない。これには組織階層を減らすことで人件費を抑制しつつ意思決定を速くしようという意図もあった。これに伴い「ティール組織」や「アジャイル組織」も喧伝された。ところが一定の規模の企業組織で階層が減少することで管理職も減少し、スパン・オブ・コントロール(管轄する部下の範囲)の拡大したのも確かである。
同時に成果主義とともに業績圧力が強くなり、個々の管理職の苦労は増加した。端的にいえば管理職一人当たりが面倒を見なければいけない部下の数が増えた。そのうえに雇用形態の多様化が一気に進み、同一職場内に非正規雇用(契約社員、パート社員)、派遣社員、外部委託社員、シニア(定年再雇用社員)、さらには外国人が増えて部下の同一性がとれなくなることで、現場マネジメントの守備範囲がますます拡大すると捉えられ始めたことも確かである。
「罰ゲーム」の具体例としてあげられるのは、管理職が部下のマネジメントや報告書の作成など、通常の業務に加えて多くの仕事をこなす必要があり、その結果、長時間労働が常態化し、プライベートの時間が減少する。管理職は部下との関係性の構築や調整を求められ、時には難しい人間関係を抱えることで心理的な負担となる…。ところが、結果として得られる報酬やさらなる昇進・昇格の機会は知れたもので、“課せられている役割責任や労力に見合ったものでない”と感じるというものだ。
もっとも、今後ともますます顕著となる労働力不足に起因する外部労働市場を巡る環境の変化、さらには働く者一人ひとりの就労意識や価値観の変容に伴って、管理職に求められる役割に変化が生まれてきた。しかし、管理職の求められる役割とは今も昔も基本的に変わるものではない。管理職が本来的に担うべき業務とは、「部下に対する支援や育成」「部門間の連携」「新たなプロジェクトへの主体的参画」である。
逆にいえばこれらの基本的な管理職の業務を担うことができない者は、そもそも管理職に就けてはならないし、管理職に就いてはならない。最近の「管理職の罰ゲーム化」という思考には、本来的な管理職の役割についての認識が乏しく、管理職を単に「権限を持つ立場」という具合に矮小化して捉えている傾向があるように思える。
このような思考の者にとっては、確かに管理職に就くということが「割の合わない」と感じることになるのは必定ともいえる。少なくとも自らの属する組織において、後輩はもとより周囲に対し、自らの習得している経験値の蓄積度合いに沿って自らを「支援や育成を行う立場」へと役割移行することの意味を認知できない者には、管理職が決してエキサイティングなものには映らず、逆に罰ゲーム的な認識が生まれるのは当然でもある。
| 一覧へ |
![]()