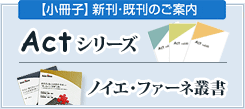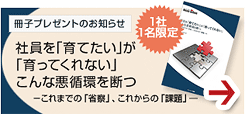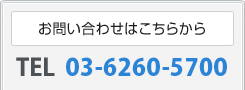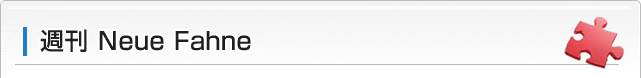人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年09月08日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-12-部下と率直、対等、誠実な姿勢で向き合う
職場において、世代ごとの特徴や価値観の違いが注目されるようになって久しい。とりわけ日本では、バブル崩壊後の就職氷河期やリーマンショックを経験した世代、いわゆるミレニアル前期と後期世代、さらに「ゆとり教育」を受けた世代やZ世代が職場で共に働いている。こうした社会的背景や教育制度の変化を受けた世代論は、しばしば語られる。
しかし、それらを安易に一般化し、部下を「○○世代だから」と決めつけて接することは危うい。むしろ個々人の価値観や経験は多様であり、同じ年代に属していても考え方や働き方は大きく異なる。管理職として必要なのは、表面的な世代区分に依拠するのではなく、部下一人ひとりの背景や思考を丁寧に理解する姿勢である。
多様性が重視される現代社会では、共通の価値観を当然の前提とする時代ではない。世代間だけでなく、性別、キャリア観、生活スタイルなど、多くの点で価値観の相違が存在する。その違いを尊重することは、組織における信頼関係の基盤をつくる一方で、摩擦や衝突の契機にもなる。特に管理職は、価値観の違いに直面したとき、怒りや苛立ちを覚えることがある。こうした感情を無自覚のままぶつければ、パワーハラスメントや信頼喪失に直結し、部下の成長や組織の活力を大きく損なう。ここで重要となるのが「アンガーマネジメント」の考え方である。
アンガーマネジメントは1970年代のアメリカで提唱され、教育や企業研修に広く普及してきた。これは単に怒りを抑え込むのではなく、「怒りと上手に付き合う」ための心理的トレーニングである。自分で変えられない状況に対しては冷静に受け止め、変えられる状況に対しては自分の感情を相手に適切に伝える。その際に大切なのは、率直でありながらも相手を尊重する表現である。怒りを正しく扱うことができれば、単なる感情の爆発ではなく、相互理解や信頼関係の深化へとつながる。すなわちアンガーマネジメントとは、怒りを抑圧するのではなく、問題解決に活かすための思考と技術なのである。
この実践の中核にあるのが「アサーティブ・コミュニケーション」である。アサーティブとは、相手の意見を尊重しつつ自分の意見を率直に表現する姿勢を指す。ここでは「率直」「対等」「誠実」「自己責任」の四つが重要な柱となる。まず、率直さは自分の考えを曖昧にせず、明確に伝えることを意味する。しかしそれは自己中心的な主張ではなく、相手の立場や気持ちを考慮したうえでの表現でなければならない。次に、対等さは、役職や年齢に依存しない人間同士の関係を基盤とする。
部下であっても一人の自律した社会人として向き合う姿勢が求められる。さらに、誠実さは自分の言動に責任を持ち、信頼を裏切らない態度を示すことにほかならない。そして最後に、自己責任の理解が欠ければ、感情を他者に押し付けるだけになってしまう。自らの感情の管理者は自分自身であることを自覚することが不可欠である。
このような姿勢をもって部下と向き合うとき、世代論による安易な決めつけは不要となる。むしろ、各世代が背負ってきた社会的文脈を理解しつつも、それを固定観念として押し付けるのではなく、対話を通じて個々の価値観や行動の意味を探ることができる。たとえば、Z世代の若手が倹約志向を示したとき、それを「最近の若者は消費しない」と片づけるのではなく、不況下で育った家庭環境や将来への不安といった背景を理解すれば、彼らの行動は理にかなったものとして受け止められる。その理解のうえで、職場でどのように力を発揮できるかを共に考えることこそが、管理職の役割である。
結局のところ、部下と向き合う姿勢の核心は、世代や価値観の違いを乗り越え、率直で対等かつ誠実な関係を築くことである。安易な世代論に依存せず、怒りを感情的にぶつけるのではなく、アンガーマネジメントを通じて冷静に自己表現する。こうした実践が積み重なることで、職場には相互理解と信頼が生まれ、部下の主体性が引き出される。上司と部下が互いに敬意を持ちつつ意見を交わす環境こそ、変化の時代を生き抜く組織の土台となる。
| 一覧へ |
![]()