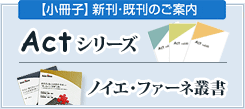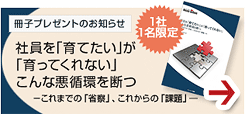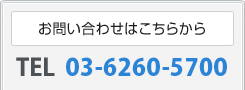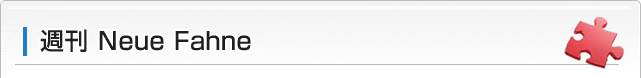人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年09月01日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-11-部下を「叱る、怒る」と指導の関係性
現代の職場において「怒る」という行為は、ほぼ全面的に否定される時代を迎えている。ある調査によれば、新入社員期に上司や先輩から一度も叱責されなかった割合は、約20年の間に9.6%から25.2%へと大きく増加している。かつてなら「優秀だから怒られない」「問題児だから怒られる」と単純に説明できたかもしれない。しかし今や、それは若者側の変化ではなく、明らかに大人の側が怒らなくなった結果である。
背景には「一切怒るな」という企業内での指導方針の広まりがある。アンガーマネジメントが浸透し、怒る人は病的であり、人前で怒ること自体が恥ずかしく、避けられるべき行為だという認識が強くなった。ここで注目すべきは「怒ることは教育効果が薄いから控える」のではなく、「怒るという行為そのものを社会規範として否定する」時代的な流れが形成されている点である。
現場では単に「怒る」と「叱る」を峻別して済むような単純な話ではない。アンガーマネジメント研修では「感情をぶつけるのが怒る、相手を否定せず改善点を伝えるのが叱る」といった整理が語られるが、実践の現場ではその区別は往々にして空虚に響く。実際、ある大企業の管理職は「怒るか叱るかはもはや問題ではなく、いかなる形であれそれに類する行為自体をやめろと研修で指導される」と語っている。
つまり、怒る/叱るの区別は、結局「自分は怒ったのではなく叱ったのだ」と弁明するための方便にもなりかねない。ハラスメント防止の観点からは「疑わしきは禁止」という厳格な姿勢が取られ、結果として管理職は「怒ることはもちろん、叱ることすら避ける」方向に追い込まれているのである。
この状況を単に上司の弱腰と見るのは早計だ。上司は個人として感情をぶつけているのではなく、組織から委任された「経営権の分担行使者」として役割を担っている。経営学者チェスター・バーナードが唱えた「組織人格」という概念に照らせば、上司は自分の人格とは別に、組織の人格を代弁し行動していることになる。従って、「個人的には注意すべきと思っても、組織人としてはスルーする」「逆に個人的には関心がなくても、組織人として叱責する」という状況が起こりうる。
とりわけ大企業では、コンプライアンスやリスク管理の観点から管理職研修が徹底され、怒る・叱るといった行為はより強く制限される傾向にある。これは組織にとっては合理的であり、社員教育に投資する「良い会社」の証でもあるが、その結果として現場の上司はますます「怒らないこと」を強く求められているのである。
結局のところ、部下を叱らないのは「若者が優秀だから」でも「上司が寛大だから」でもなく、「組織が揉め事を避けたいから」という単純かつ冷徹な理由に帰着する。だが、この事情は上司には明確に見えていても、若手社員からすれば知る由もない。彼らは「怒られない=自分が十分にできている」と解釈するかもしれないし、逆に「何も言われない=放置されている」と不安を募らせるかもしれない。
そこで重要になるのは、怒らずとも部下の成長を支える方法を工夫することである。例えば、事実に基づいたフィードバックを短いサイクルで伝える、期待値と現状のギャップを客観的に共有する、改善の行動を一緒に設計する、といった手法が求められる。上司の役割は「怒るか叱るか」を選ぶことではなく、「怒らない前提でどう伝えるか」を設計することに移行しているのだ。怒りを封印することで指導の余地がなくなるわけではなく、むしろ部下の主体性を引き出す余地が広がる。叱責の喪失がもたらす空白を埋めるのは、感情ではなく構造化された対話であり、それこそが現代的な指導の核心といえるだろう。
| 一覧へ |
![]()