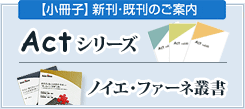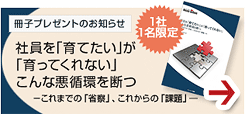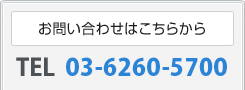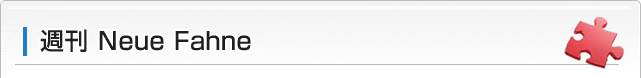人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年08月25日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-10-部下に当事者意識を持たせる
部下を育成する上で重要なのは、単に業務を指示して遂行させることではない。部下自身が自らの仕事に主体的に向き合い、責任感を持って取り組むように導くことである。そのためには、まず部下に「当事者意識」を持たせなければならない。
上司がどれほど管理を徹底しても、部下が心の底から仕事に本気で取り組もうとしなければ、成果は一時的なものにとどまってしまう。当事者意識の欠如は、部下の不安や迷いを増幅させ、結果的に組織の力を削ぐ。だからこそ、上司には「部下に当事者意識を芽生えさせる仕組み」を作る責務がある。
その第一歩は、上司自身が語る「方向性」を明確に示すことである。会社を通じて社会にどのような価値を提供しようとしているのか、自分の理想とどのようにつながっているのかを、自らの言葉で語る必要がある。上司の姿勢に使命感がにじみ出ていれば、部下はその熱量に共鳴し、安心して努力できるようになる。逆に、部下を単なる「業績を上げるための道具」として扱えば、不安や不信感は増すばかりである。ここで効果的なのは、定期的な1on1ミーティングである。単なる業務報告の場にするのではなく、「会社が向かおうとしている方向性」と「部下の成長の方向性」を結びつける対話を行うことが重要だ。
部下にとって自分の努力が会社の大きな流れとどのようにつながっているかを理解できれば、不安は薄れ、挑戦意欲が生まれる。また、日常の業務指導においても「この仕事を通じてどんな力が身につくのか」「それが今後のキャリアにどう役立つのか」を具体的に伝えることが望ましい。部下育成とは、仕事をこなすために人を訓練することではなく、「部下を育てるために仕事がある」と捉えるべきだからだ。こうした姿勢を持つ上司のもとでは、部下は自然とやる気に火をつけ、自ら挑戦しようとする。
方向性を語るだけでは十分ではない。部下に当事者意識を持たせるには、経営に関する情報を共有し、仕事を「経営全体の一部」として位置づけて理解させることが欠かせない。部下が本気で働けない背景には、「自分の仕事が会社全体の中でどのような意味を持つのかが分からない」という不安が潜んでいる。上司が知っている経営情報を部下に伝えなければ、部下は自分の役割を俯瞰できず、当事者としての意識も芽生えにくい。そこで有効なのが、定期的な経営情報共有会である。部門会議やチームミーティングの場で、会社全体の数字や戦略、今後の展望を簡潔に伝える。例えば「この四半期の売上が全社計画にどう貢献しているか」「新規事業が立ち上がることで、部門の役割がどう変わるか」といった情報を共有することで、部下は自分の仕事の背景を理解できる。
仕事を会社全体の中で位置づけて説明する姿勢も不可欠だ。例えば「このプロジェクトが進めば市場での競争力がどう高まるのか」「部署の成果が全社の収益にどんな影響を与えるのか」を具体的に伝える。こうした言葉があるからこそ、部下は自分の業務を単なる作業としてではなく、経営に直結した役割として捉えられるのである。また、部下は常に「自分の将来」を意識していることを忘れてはならない。いまの仕事が将来のキャリア形成やスキル習得にどうつながるかを、上司が具体的に示してやる必要がある。例えば「この業務で培った分析力は、次のリーダー候補に欠かせない」「この経験は三年後の新規事業に直結する」などと伝えれば、部下は成長の実感を持ちやすくなる。
最終的に、部下が当事者意識を持ち、本気で取り組むようになるためには、上司の二つの役割が重要である。第一に、明確な方向性を語り、部下に安心感と挑戦心を与えること。第二に、経営情報を共有し、部下の仕事を会社全体の中で意味づけることである。これを実践するために、1on1ミーティングで方向性を共有すること、経営情報を定期的に伝えること、そして仕事の成長効果を具体的に示すことが欠かせない。
部下を育成するとは、単に成果を出させることだけではなく、部下自身に「自分は会社を動かす一員である」という実感を持たせることだ。当事者意識を持った部下は、不安を乗り越え、自ら考え行動する。そうした部下の姿勢こそが、組織全体を持続的に成長させる原動力になるのである。
| 一覧へ |
![]()