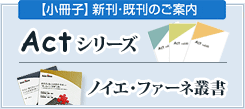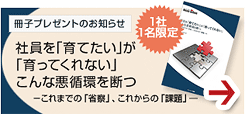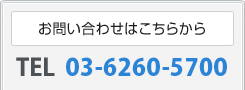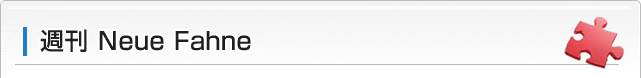人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年08月04日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-9-明確な使命感が部下の共感を呼ぶ
管理職の本質的な役割とは、単に日常業務を管理し、部下に指示を与えることのみにあるのではない。むしろ、その力量が真に問われるのは、突発的に発生する例外事象に際してである。たとえば、顧客からの厳しい苦情、突如として持ち上がった取引上のトラブル、あるいは社内不祥事等、即時の判断と行動が迫られる局面において、管理職自らが前面に立ち、速やかに対応せねばならない。
定型的な日常業務においては、部下に処理を任せ、その進捗を管理することが管理職の本分である。しかし、例外事に関しては、その処理の実行責任者たるべきは、他ならぬ管理職である。即断即決を要する場面においては、現場における判断と対応の権限を併せ持つ者でなければ、事態の収拾は覚束ない。こうした一件一件の対応において、部下は上司の姿勢をつぶさに観察し、そこからその人間性や価値観を見極めている。
部下は、常に上司の言動に注視している。とりわけ、「この場面は上司が出てくるべき局面である」と心中において感じたとき、その期待に応じる上司か否かによって、部下の評価は大きく変わる。たとえば、重要会議を調整してでも苦情対応にあたる管理職の姿を見たとき、部下はその業務の優先順位を認識し直し、「この仕事はかくも重大なものであったのか」と、上司の判断力に信頼を寄せるようになる。
反対に、部下が内心で「ここは自分ではなく、上司の判断が必要だ」と考えているにもかかわらず、当の上司が曖昧な態度をとるならば、部下は大いに失望するに違いない。管理職たる者は、部下が無言で寄せてくる期待に気づき、適切に応えるだけの感受性と覚悟を持ち合わせていなければならない。
部下からの期待に確実に応じるためには、管理職自らが確固たる使命感を持つことが不可欠である。使命感が曖昧であれば、言動に一貫性が失われ、部下に対して誤ったメッセージを発することになる。たとえば、上層部に対する批判を公然と口にし、組織の課題を他人事のように論じ、さらには諦念を漂わせる言動をとるような上司がいたとして、部下がそのような人物に信頼や共感を寄せることはない。
部下はそうした姿勢に触れるたび、「この職場でこの先も働いていて良いのか」と深い不安を抱くに至る。多少の不満であれば、部下の認識や姿勢によって乗り越えることも可能であろう。しかし、上司の姿勢そのものが生む「不安」は、部下の心を深く蝕み、やがては離職や組織への無関心といった形で表出することになる。
管理職は、何よりもまず己の仕事に対し使命と誇りを持ち、組織の将来に希望を見出し、その展望を明確な言葉で部下に示すべきである。どれほど困難な状況下にあっても、向かうべき方向性を語り、実践するする意義と意味を説き、部下に「状況に沿った最善の策」を訴えかけることが肝要である。
こうした前向きな姿勢と明確な使命感は、部下の心に共鳴を呼び、上司への信頼と尊敬を育む。部下が上司の方針に従い、自らも努力を惜しまぬようになるのは、上司が熱意と信念に満ちた行動を日々重ねている場合である。部下の期待に応え、使命感を行動で示す管理職こそが、組織の要となり、変化と困難を乗り越える牽引力を備えた存在となる。
| 一覧へ |
![]()