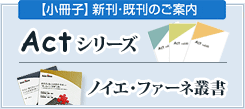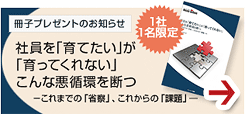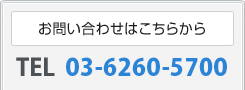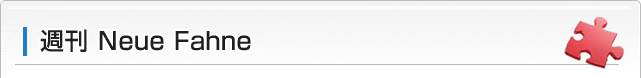人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年07月28日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-8-職場環境づくりと部下への支援行動
組織の業績は、個々の能力や努力だけで決まるものではない。むしろ、その基盤には「職場の環境づくり」が不可欠である。働く人々が活き活きと仕事に取り組むためには、やる気を引き出すような職場風土を整えることが前提であり、その責任は職場を率いる管理職にある。管理職がいかに環境を整え、部下を支援していくかが、結果として組織全体の生産性やモラールに直結していく。
職場において、「仕事がおもしろい」と部下が感じているかどうかは、管理職の目配りによって大きく左右される。もし部下が「人生の切り売りで給料をもらっている」と感じているとしたら、それは仕事にやりがいを見出せていない証拠である。こうした状況に対して、部下の責任感の欠如を叱るのではなく、まずはその背景にある職場環境の問題に目を向けるべきである。やる気や動機づけも重要だが、それを活かすためには整った環境が前提となる。
管理職が配慮すべき環境整備には、いくつかの具体的な視点がある。
第一に、仕事の準備や計画、指示が充分に行われているかという点である。各人の役割が明確であり、自らの仕事が組織に貢献していると実感できること。さらには、適切な仕事を切れ目なく与えつつ、必要な支援は惜しまないが、最終的には部下の力でやり遂げさせるような采配が求められる。
第二に、職場に「けじめ」が保たれているかが問われる。礼儀や規則、緊張感、安全意識、整理整頓といった基本が徹底されていることが、日々の業務の精度とスピードに直結する。
第三に、職場の雰囲気として「明るさ」や「人間味」があるかどうかも大切だ。人間関係が円滑で、悪意ある争いがなく、上司がコミュニケーションの中心にいる状態を作り出せれば、自然と活気と前向きな対話が生まれ、組織のエネルギーが高まる。
部下を育てていくうえで欠かせないのが「支援行動」である。ここで重要になるのが、その“サジ加減”である。よく知られている言葉に「育たなかったのは教えなかったからだ。育たなかったのは教えたからだ」という一見矛盾した表現がある。これは、教えなければ部下は育たないが、教えすぎても成長の機会を奪ってしまうという、支援の難しさを表している。支援が少なければ成果は出ず、多すぎれば依存心を助長する。タイミングもまた重要であり、早すぎれば過保護に、遅すぎれば自信喪失や失敗につながる。
では、どのように支援すればよいのか。まず、「初めから正解を与えるのではなく、答えを小出しにして部下自身に考えさせる」姿勢が必要だ。試行錯誤する中で、部下は自力で正解にたどり着く力を養う。このプロセスを奪ってしまえば、部下は自分で問題を解決する力を身につけることができない。次に、「大きな障害だけは取り除いてやる」という判断も重要である。本人の努力ではどうにもならない障害を放置すれば、部下はただ徒労に終わる。これでは育成どころか、モチベーションを失わせることになりかねない。
実務の現場では、一定の成果を上げながら育成を並行させる必要がある。そのためには、いくつかのフォローが求められる。例えば、進捗が遅れている仕事にはスピードアップの指導を行い、損害が予測される業務については最初から正解を示す。また、効率が落ちている場合には軌道修正を促す。こうしたフォローは、単なる「手助け」ではなく、部下が自信を失わず、成長につながるための「仕組まれた支援」である。
職場の環境づくりと部下への支援行動は、決して別々のものではなく、一体の取り組みである。環境が整っていてこそ、支援が効果を持ち、支援の質が高ければ、職場の雰囲気や文化にも良い影響を及ぼす。管理職の役割とは、ただ指示命令を出すことではなく、部下が最大限に能力を発揮できる場を作り、その中で自ら成長していけるように導いていくことである。その実現のためには、環境整備と支援行動を両輪として機能させる視点が不可欠である。
| 一覧へ |
![]()