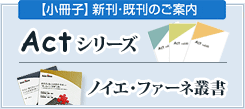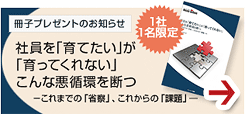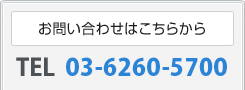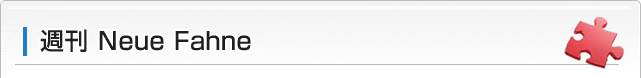人材育成が社員と会社組織の協働を創りだす
2025年07月14日号
“働き方”と“管理職の在り方”に絡む思念-7-部下との接し方と評価実践
職場における上司と部下の関係は、単なる業務上の上下関係にとどまらず、組織の成果と風土に大きな影響を与える重要な要素である。部下の力を引き出し、育成し、信頼関係を築くためには、日々の接し方や評価のあり方を見直すことが欠かせない。とりわけ、現代の若手社員は、上司との関係性に敏感であり、その対応いかんでモチベーションが大きく変動する。従って、上司としての基本的な姿勢と実践的な行動を改めて確認しておく必要がある。
前提として重要なのは、直属の上司が部下に対して責任を持つという意識である。部下の面倒を見るのはあくまでも直属の上司であり、その責任を他人任せにしてはならない。具体的には、ルールや業務の期限、求める水準を明確に示し、分かりやすく丁寧な説明を心がけることが求められる。指導というよりは“教える”“訓練する”というスタンスをもち、部下が躊躇している場面では、ためらわずに手を差し伸べる「介入」の姿勢が必要である。
年長者や上司は「わかったふり」をせず、自らも学び続ける姿勢を見せるべきである。若者は“現役選手”を尊敬する傾向が強いため、上司が挑戦を続ける姿勢を見せることが、部下からの信頼につながる。「自分もこういう失敗をしたが、こう乗り越えた」といったリアルなエピソードは、若手の心に響く。逆に、過去の武勇伝や自慢話は、彼らにとっては無関係かつ時に有害であり、反感を抱かれる原因になりかねない。
部下の評価において最も重要なことは、「高い評価」よりも「早い評価」である。部下が提出した報告書や提案書を、忙しさを理由に数日放置したり、何もコメントせずに済ませたりするのは、部下のやる気を大きく削ぐ行為である。たとえ的確な評価であっても、時間が経ってからでは効果は薄く、モチベーションの向上にはつながらない。提出物を受け取ったら、その場で評価し、コメントを添えてフィードバックを返す。この「即応性」こそが、部下との信頼関係を築く鍵となる。
日常的な報告や相談についても同様である。部下の努力や苦労、試行錯誤をしっかりと受け止め、評価し、言葉にして伝えることが求められる。上司が部下の仕事の価値を認識し、それを即座に示すことで、部下は自分の仕事が認められていると実感し、次の行動につなげやすくなる。たとえミスがあったとしても、その過程や工夫を汲み取り、単なる叱責ではなく、改善への道筋を示す対応が望まれる。
こうした接し方や評価の根底にあるべきものが「人望」である。どれだけ知識や経験があっても、人間的に信頼されていない上司には、部下は真の意味でついてこない。人望とは、部下の価値を正しく認め、丁寧に評価し、誠実に接することで築かれるものである。上司が自らの立場や肩書を盾にして強圧的に接すれば、部下は表向きには従っているように見えても、心の内では離れていく。年齢や学歴を過度に振りかざすことも、敬遠される原因となる。上司が上司である前に一人の人間として、相手を尊重する姿勢がなければ、部下との信頼関係は築けない。
部下との関係において重要なのは、権威ではなく信頼である。信頼は、日常の小さなやりとりの積み重ねから生まれる。わかりやすく教える、すぐに反応する、誠実に評価する、これらの行動が揃って初めて、上司としての「人望」が育まれていく。そして、その人望こそが、部下を動かし、組織全体を前向きに変えていく原動力となる。
結局のところ、部下は上司の言葉ではなく、その姿勢と行動を見ている。部下に誠実に向き合い、信頼関係を築くことこそが、上司としての基本であり、評価の実践である。難しいことではないが、疎かになりやすい。だからこそ、目的意識性をもって実践し続けることが、何よりも大切なのである。
| 一覧へ |
![]()